「チャレンジタッチって効果あるの?」「ウチの子には向いているの?」そんな疑問について、わが家のリアルな体験談をお届けします。
- チャレンジタッチで感じた効果7つ
- 辞めた理由は学びの質にモヤモヤしたから
- ウチの子どうかな?「向き不向きチェックリスト」
- 我が家の体験談
我が家では息子が小3の終わりから小4までの約1年間、チャレンジタッチを利用していました。
キャラクターの声かけやゲーム感覚の学習スタイルは、子どもの「やってみたい!」を引き出すように設計されています。
実際、息子の学習のきっかけとしては非常に優秀だと感じました。
ただ、進めるうちに「なんとなく解いて終わりにしてしまう」ことが増え、少しずつ違和感も。
結果として我が家はチャレンジタッチを辞め、公文式に切り替えることにしました。
しかし「効果がないからやめた」というよりも、「子どもや家庭によって向き不向きがある」と感じたのが正直なところです。
この体験を通じて、チャレンジタッチの魅力と、辞めた理由をあわせて率直にお話しします。
チャレンジタッチの効果|予習や習慣付けが楽しくできる
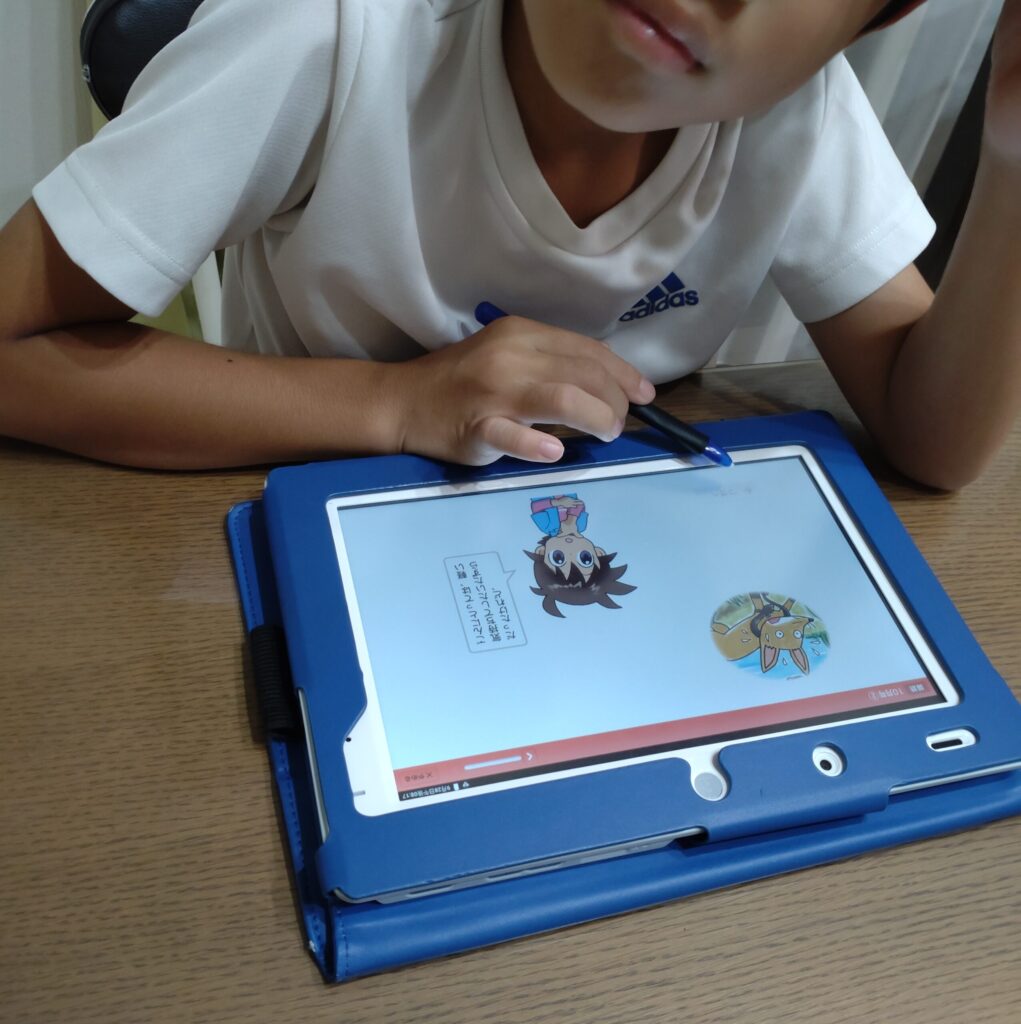
チャレンジタッチは、「新しいことをすぐに理解するのが難しい」我が子にとって、予習を通じて“学習のとっかかり”をつかむ助けになる教材でした。
前提として息子の性格や特徴について紹介します。
- 自分の気持ちを言葉にするのが苦手
- ルールをすぐに理解するのが難しい
- 嫌なことに対して気持ちを切り替えるのに時間がかかる
初めて見る問題や文章に対しては強い苦手意識があり、学年が上がるにつれ学校の授業についていくのが難しいと感じる場面が増えてきました。

何この問題!わかんない!!
そんな中、チャレンジタッチの“先取り学習”は子どもにとって安心材料に。
あらかじめ見たことのある内容が学校で出てくることで、「これ、わかる!」という自信につながったようです。
- 先取り学習で授業に余裕を持って取り組めるようになった
- ちょっと難しい問題も積み上げることで解き方を自然にマスターできる
- アプリが充実しているのでレベルに合わせた学習が可能
- 全教科網羅型なので満足度(安心感)がある
- 動画やわかりやすい図解で視覚的に理解が深まる
- アラーム機能で学習の習慣化ができる
- ごほうびシステムでやる気が持続する
チャレンジタッチは「自学が得意な子」だけでなく、「理解するのに時間がかかる子」「学習に苦手意識を持ちやすい子」にとっても、学びへの入り口を広げてくれる教材だと感じました。
【効果①】先取り学習で授業に余裕を持って取り組めるようになった
チャレンジタッチは学校より少し先の内容を学べるため、授業が復習になり理解が定着しやすくなります。
チャレンジタッチの先取り学習は、無学年方式で子どもの理解度に合わせて国語・算数の問題が出題され、無理なく進められるのが特長です。
成功体験が増えることで自己肯定感が育まれ、学習意欲も向上。
学校の授業内容がよりスムーズに理解できるようになるため、苦手意識や勉強嫌いの予防にもつながります。
例えば算数で予習していた内容が授業で出てきたとき、自信を持って発言できたことも。
余裕が生まれると苦手意識が減り、前向きな学びの姿勢が育ちます。
【効果②】難しい問題は順序立てて解き方を自然にマスター
レベルに応じた段階的な問題構成で、少し背伸びした内容にも挑戦できます。
問題ごとに動画や音声によるわかりやすい解説があり、操作しながら考え方を視覚的・聴覚的に確認できるのが特長です。
自分に合った問題やヒントを提示してくれるため、「どこでつまずいたのか」が明確になり、つまずき部分を重点的に解消できます。
徐々に理解を積み上げ、自力で解き方を身につけることが可能です。
【効果③】アプリが充実!レベルに合わせた学習ができる
チャレンジタッチは、多彩な学習アプリが揃っており、子どもの理解度や興味に合わせて使い分けが可能です。
主要5教科の「メインレッスン」アプリをはじめ、ふりかえり復習レッスンで学習の定着を図れます。
他にもプログラミング学習の「プログラミングワールド」、英語4技能対応の「Challenge English」など、多様なアプリで学習を深められます。
4年生では都道府県を楽しく学べるゲーム形式のアプリもあり、楽しみながらレベルに合った学びを進められました。
【効果④】全教科網羅型なので満足度がある
チャレンジタッチは、国語・算数・理科・社会などの主要教科に加え、英語・プログラミングといった現代的な学習分野まで網羅しています。
これは学習指導要領に沿った設計になっています。
教科書ごとの単元に対応し、予習・復習のしやすさや、標準・発展レベルの選択も可能。
さらに前学年の復習や赤ペン先生の添削指導、約1,000冊の電子書籍なども付属し、家庭学習の幅を広げてくれます。
すべての教科書内容を完全に網羅しているわけではありませんが主要教科においては高い網羅性があります。

「これさえあれば安心」と思える満足感を得られる学習設計になっています!
【効果⑤】動画やわかりやすい図解で視覚的に理解が深まる
チャレンジタッチではアニメーション動画や図解を使って「どう考えるか」「どこに注目するか」を視覚的に示してくれます。
たとえば図形問題なら、図が動いたり色分けされたりして手順や考え方を自然に理解できます。
国語も文章構造をイラストで整理し、流れを掴みやすく設計。
さらに録画授業やライブ授業では、先生の板書や図を見ながら進められ、教室のような感覚で学べます。

ライブ授業ではアイスの工場見学があっておもしろかったな!
アプリやヒント画面にも図解が多用され、難所では段階ごとに動画と図でサポート。
目で見てわかるから、つまずきにくく自分で「なるほど!」と納得できる学習体験が可能な構成になっています。
【効果⑥】アラーム機能で学習の習慣化ができる
チャレンジタッチには「学習時間アラーム」や「コラショアラーム」などのアラーム機能が搭載されており、子どもの学習習慣化を強力にサポートします。
保護者や子ども自身が曜日・時間を自由に設定でき、設定時刻になるとキャラクター音声やメロディーでお知らせ。
アラームを止めるにはタブレットを操作する必要があるため、そのまま自然と学習に移行しやすい仕組みです。
毎日の声かけをタブレットが代わって行う形となり、親子双方の負担を減らしながら、決まった時間に学習する流れを定着させる効果が期待できます。

8時になったらタッチの時間だね。

我が家ではこれが学習習慣の定着化に大いに役立ちました!
【効果⑦】ごほうびシステムでやる気が持続する
チャレンジタッチには、学習後にごほうびとしてゲームやポイントがもらえる「ごほうびシステム」が搭載されており、子どものやる気を持続させる効果があります。
勉強を終えないと遊べない仕組みになっているため、「勉強→ごほうび」という流れが自然に身につき、学習へのモチベーションがアップ。
学習を終えると「ジュエル」や「努力賞ポイント」がもらえ、ゲーム内アイテムや実際の商品と交換できる楽しみも。

努力賞のバッグが欲しくてがんばったよ!
これにより、遊びと学びのバランスが保たれ、保護者も安心して見守れます。
実際の口コミでも「ごほうびがあるから続く」「やる気が出る」と高評価が多く、楽しく学びを継続する工夫が随所に盛り込まれています。

息子は努力賞ポイントのプレゼントページをよく眺めて楽しんでいました。
チャレンジタッチを活用していた息子ですが、1年後にはチャレンジタッチを辞めることになるのです…。
チャレンジタッチを辞めた理由は「学びの質」にモヤモヤ

チャレンジタッチは楽しく取り組める教材でしたが、我が子には「学習を深める」という面で合わず1年で辞めることにしました。
息子の場合、選択式の問題でたまたま正解することが多く、間違えた問題に関しても解き直しの際には“正しい答えを覚えてそのまま入力する”という形で済ませてしまうように。

つまり、考えるプロセスを経ずに正解にたどり着くクセがついてしまったのです。
チャレンジタッチ内のゲーム要素(アプリなど)も、簡単なものばかりやっていて学習より遊んでいる状態になっていきました。
息子の性格からも「間違えること」や「考えること」への抵抗感が強く、受け身の学習スタイルに偏っていったように感じます。
チャレンジタッチのように、テンポよく進むデジタル教材は一見すると便利に見えますが、理解が浅くても「できた気になってしまう」構造は、我が子には合わなかったようです。

チャレンジタッチそのものが悪い教材だったわけではありません。
ただ、我が子には合いませんでした。
それが辞める決断に至った最大の理由です。
合う・合わないはお子さんの性格や学習スタイルによって大きく異なると実感しました。
チャレンジタッチ向き不向きが見えるチェックリスト

チャレンジタッチには向き不向きがあり、特に「自分で学習のペースを整えられる」「視覚・操作型学習が得意」な子には相性が良く、「抽象的なルール理解が苦手」「選択肢に頼ってしまう」子には効果が出にくい傾向です。

毎日の勉強、親が全部見るのは本当に大変。
だからこそ「これなら子どもが一人でやれそう」と思えるツールに頼りたくなりますよね。
チャレンジタッチは、そんなご家庭の味方になることも多い教材。
でも、どの子にも合うわけではありません。

「どんな子に合いやすいか」をわかりやすく整理しました。
【ウチの子向いてる?チェックリスト】
| 向いてる | 向いていない |
|---|---|
| ☐ 一人で黙々とタブレット学習に取り組むのが好き | ☐ わからないとすぐに手が止まり、一人で進めるのが苦手 |
| ☐ キャラクターやごほうびにやる気を出せる | ☐ ごほうびばかりに気を取られて学習が身に入らない |
| ☐ 授業で「これ知ってる!」と予習内容に反応する | ☐ 学習時間を自分で決めたり、習慣づけるのが苦手 |
| ☐ ざっくりでも予習しておくと安心して取り組める | ☐ 選択肢をなんとなく選んで正解してもスルーしてしまう |
| ☐ 間違えた問題を見直す習慣がある | ☐ 間違えてもすぐ答えを見て終わらせてしまう |
| ☐ 同じ問題を繰り返して理解を深めようとする | ☐ なぜ正解なのか説明できず、理解があいまい |
まず、一番大事なのは子どもが前向きに取り組みたいという意欲があることです。
学習習慣などはチャレンジタッチを始めてから身に付くこともあるので、現在を基準に全て決定するものではありません。

チェックリストをやってみて、ウチの子でもできそうだな…と感じてもらえたら嬉しいです。
【チャレンジタッチ体験談】楽しく学べたけど…我が家は公文へ

チャレンジタッチは、子どもの興味を引き出し学びのきっかけをつくってくれた一方で、続けるうちに我が子には合わないと感じる場面も増え、最終的に別の学習方法へ切り替えることになりました。
チャレンジタッチは、実際に効果を感じた場面もありましたが次第に違和感を感じるようになりました。
チャレンジタッチには、子どもの「学びたい!」を引き出す仕掛けがたくさんあり、入会当初はその効果を実感していました。
ただ、わが家では続けるうちに少しずつ難しさを感じるようになり、最終的には別の学習方法に切り替えました。
初めのうちは「今日はこれやってみよう!」と子どもから声を上げることもあり、学びの入り口としてとても助かりました。

今日の分は終わったよー!イェーイ!

うーん、理解してる??
慣れてくるにつれゲーム感覚やごほうび目的で課題をこなすだけになってしまい、内容を理解せずに進めている様子がうかがえるようになりました。
実際、チャレンジタッチや赤ペン先生で解いた問題と同じ内容のテストでミスがいくつも見られるようになりました。
チャレンジタッチには、子どもの興味を引き出す工夫がたっぷり詰まっていて、学びの第一歩としては本当に心強い教材だと感じます。
でも、子どもの特性や性格によって続けやすさには差が出ると実感。
そこから息子の場合は、繰り返し学習が向いていると思い公文式に切り替えていますが、チャレンジタッチを通じて得た「楽しく学ぶ姿勢」は今も活きています。

公文をやっている体験談は次の記事で紹介しますね。
まとめ

チャレンジタッチには、子どものやる気を引き出す工夫が多くあり、我が家でも「学ぶ楽しさ」を知る良いきっかけになりました。
- チャレンジタッチは、新しいことの理解が苦手な我が子にとって、予習で学習のとっかかりをつかむ助けになった
- チャレンジタッチを1年で辞めた理由は「学習を深める」という面で合わなかったから
- チャレンジタッチは、自分で学習ペースを整えられ視覚的な学習が得意な子に向いていて、抽象的な理解が苦手で選択肢に頼りがちな子には合いにくい傾向
- チャレンジタッチは学びのきっかけにはなったものの、続けるうちに合わないと感じ、公文式に切り替えた
効果も感じていた一方で、進め方や習慣化の面でつまずくこともあり、最終的には合わないと感じて辞めました。
この体験談を通じて伝えたいのは、「チャレンジタッチが良い・悪い」ではなく「向き不向きがある」ということ。
どの教材にも一長一短があります。
もし今、続けるか迷っているなら、お子さんの様子やご家庭のスタイルに合うかを見つめ直すタイミングかもしれません。
あなたの選択が、お子さんにとってより良い学びにつながりますように。
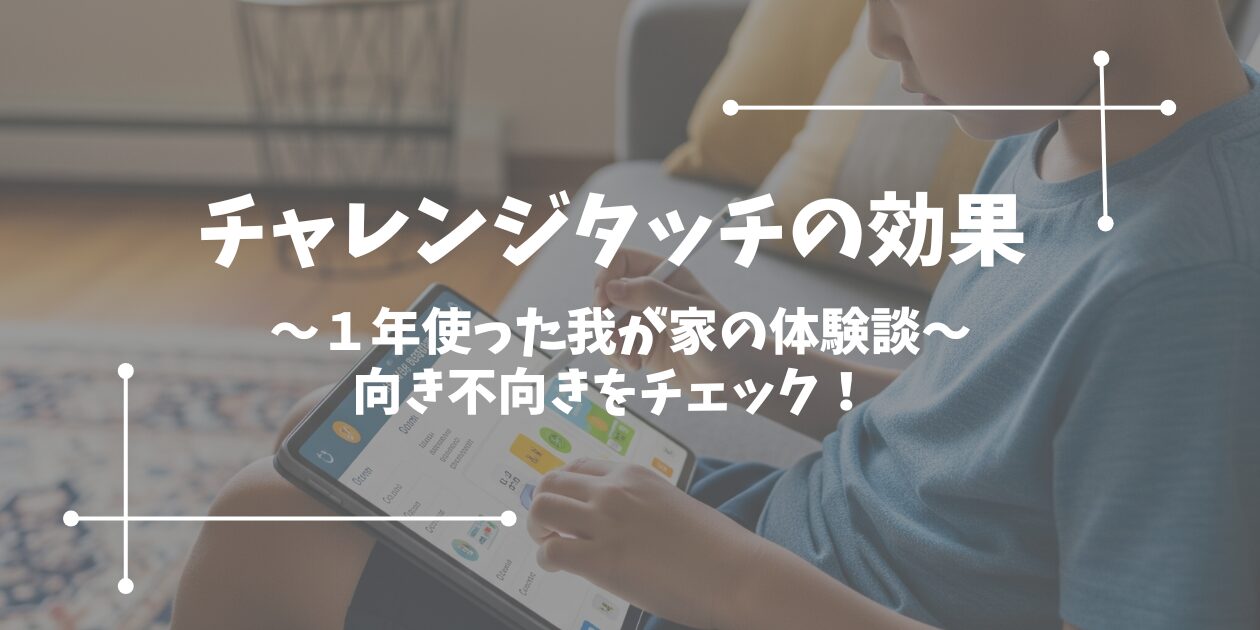


コメント